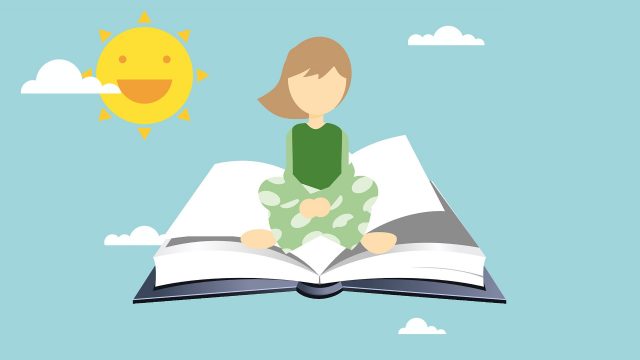こんにちはユキです。
結婚式や葬式など、慶弔の場でお祝いやお悔やみの挨拶をすることがよくありますが、あなたは上辺だけの挨拶で満足していますか? それとも気の利いた挨拶をしたいと思っていますか?
この記事では慶弔の場で気の利いた挨拶をするにはどうすればいいのか、私なりに考えて実行したことをご紹介します。
挨拶の苦手な人に参考になれば幸いです。
慶弔の場で挨拶はとても大事
慶弔対応の中で挨拶をすることがたくさんの場面であります。
例えば、結婚のお祝いを贈るときに新郎新婦や新郎新婦のご両親にする挨拶や、葬式のときにご遺族にする挨拶です。
あなたは結婚式や葬式に出られたときに、どのような挨拶をされるでしょうか。
結婚式の場合、例えば新婦の父への挨拶は「この度はお嬢様のご結婚、誠におめでとうございます。末永くお幸せになられますことをお祈りいたします。」という内容でも構わないと思いますが、その父親が妻を亡くし男手一つで娘さんを育てたということを知っておれば、「お喜びの中にも一抹の寂しさもあるかと思いますが、お嬢様はきっとお幸せになると思います」というような気の利いた挨拶ができます。
葬式の場合も、故人の妻に対して「この度はご愁傷様でございます。ご主人様のご冥福をお祈りいたします。」でも良いのですが、夫が前日まで元気だったのに、朝に突然亡くなっていたという状況を知っておれば「突然にご主人を亡くされ、とても残念だと思いますが、お気持ちをしっかりお持ちくださいますようお願いします」という挨拶ができます。
慶弔の場において、このような気の利いた挨拶をするためには、挨拶のことを深く知り、日頃から挨拶に関心を持つことが大事だと思います。
そもそも挨拶って何?
挨拶の意味を辞書で調べてみますと、次のように書かれていました。
〔仏〕禅家で、問答を交わして相手の悟りの深浅を試みること。
うけこたえ。応答。返事。
人に会ったり別れたりするとき、儀礼的に取り交わす言葉や動作。
儀式・会合などで、祝意や謝意、親愛の気持、あるいは告示などを述べること。また、その言葉。
(「御―」の形で)相手の挑発的な、礼を失したような言動を皮肉っていう語。
仲裁。仲裁人。
紹介。紹介者。
人と人との間柄。交際。
この中で、私たちが挨拶として認識している意味は、やだと思います。
でも、挨拶の「挨」と「拶」という字の、それぞれの意味を調べてみると、もっと奥深いものだということがわかりました。
「挨」は、おす・ひらく・おしのけるという意味で、「拶」は、せまる・おしよせるという意味だそうです。
このことから挨拶というのは、相手の懐に迫り、相手の心を押し開くという意味だと解釈しました。
ですから挨拶をするときは、相手の心の内に分け入って、自分の気持ちを伝えることが大切ではないかと思いました。
このことを知るまで私は挨拶をするときに何も考えないで、ただ儀礼的に「おはようございます」とか「こんにちは」と言っていたような気がします。
挨拶で大事なこと
挨拶で気持ちを伝えることが大事だと思う
挨拶の 本当の意味を知ったからには、それを実行しようと思いました。
それには日常の挨拶をするときに、相手の心の内に分け入って、自分の気持ちを伝えなければいけません。
例えば朝早く、出勤する近所の人に会ったとします。
そのときに、その人の心の内に分け入ると、「朝早くから出勤するのは辛いな」という声が聞こえてきます。
ですからその人に伝えたいのは、「朝早くからしんどいのに、ご出勤お疲れ様です。今日があなたにとっていい一日でありますように。」という気持ちです。
そのような気持ちを、「おはようございます」という挨拶に込めることにしました。
そうすると、なんだか声のトーンも変わり、相手の反応もいつもと違うような気がしました。
他の挨拶も、次のような気持ちが大事ではないでしょうか。
こんにちは:お元気ですか? 今日があなたにとっていい日でありますように。
こんばんは:一日のお勤めお疲れ様でした。今日も良い日でしたか?
おやすみなさい:良い睡眠でゆっくり休んでください。
さようなら:また逢う日までお元気で。
いってらっしゃい:無事に帰ってきてくださいね。
おかえりなさい:お疲れ様でした。
英語の挨拶でもmorning、afternoon、evening、nightの前にgood をつけますよね。
これも同じように、「あなたにとって良い朝でありますように」とか、「あなたにとって良い昼でありますように」・・・・・というような気持ちを伝える言葉ではないかと思います。

挨拶は、心・言葉・行動の三位一体が大事だと思う
挨拶では気持ちを伝えることが大事だと申し上げましたが、その前にまず自分が相手を思いやる心、相手との関りを良好にしようとする心を持つことが大事だと思います。
その気持ちがなければ、挨拶をしても上辺だけの薄っぺらいものになってしまうと思います。
その心を伝えるには言葉が大事になります。
心はあるのですが、それを言葉で上手く表現できないときがあります。
言葉を飾ったり、言葉が足りなかったり、余計なことを言ってしまったりして、あとから自分は相手に何を言いたかったのだろうかと思うことがよくあります。
自分の心を言葉にするには、あまり考えないで、自分の気持ちに素直になり、ありのままの気持ちを言葉に出せば良いのではないかと思います。
そして、マイナスの言霊を発するのではなく、プラスの言霊を発することも大事だと思います。
口の中でもぞもぞ言うのではなく、はっきりと言葉を発することは言うまでもありません。
先ほど「挨」はおす・ひらく・おしのけるという意味で、「拶」は、せまる・おしよせるという意味で、挨拶とは相手の懐に迫り、相手の心を押し開くというように解釈できると申し上げました。
ですから、挨拶をするときには相手に近づき、相手の胸をこじ開けるという行動をとることも大切だと思います。
勿論、実際にはそのようなことはできませんので、そのような行動をとる意識をするということです。
そうすれば、自ずと視線は相手の目にいき、真っすぐ相手に向き合う態度になると思います。
このように、心・言葉・行動のどれも欠けることなく、三位一体であることが、きちんとした挨拶の条件だと思います。
それによってコミュニケーションを図ることができ、お互いが快適な気持ちになるのではないでしょうか。

最後に
慶弔の場で挨拶をするのが苦手な人も、挨拶の本質を知り、普段から心を込めた挨拶をしておれば、結婚式や葬式に行っても、気の利いた心のこもった挨拶ができ、挨拶を受ける相手に良い印象を与えます。
日々の訓練が慶弔の場だけでなく、いろんな場面で役に立つと思います。
この記事のポイントをまとめますと次のとおりです。
慶弔の場において、気の利いた挨拶をするためには、挨拶のことを深く知り、日頃から挨拶に関心を持つことが大事。
挨拶の「挨」は、おす・ひらく・おしのけるという意味で、「拶」は、せまる・おしよせるという意味。
きちんとした挨拶をするには、相手のことを思いやる心、その心を伝える言葉、相手に迫り相手の胸を押し開く行動、それらが三位一体となることが大事だと思う。
日常できちんと挨拶ができるようになれば、慶弔の場だけでなく、いろんな場面できちんとした挨拶ができるようになると思う。
以上のように挨拶ってとても奥が深いと思います。
翻って自分がしている挨拶を考えると、きちんとした挨拶には程遠いように思います。
言うは易く行うは難しです。
このような記事を書いたのですから、私自身が少しでも良い挨拶ができるよう、心がけたいと思います。