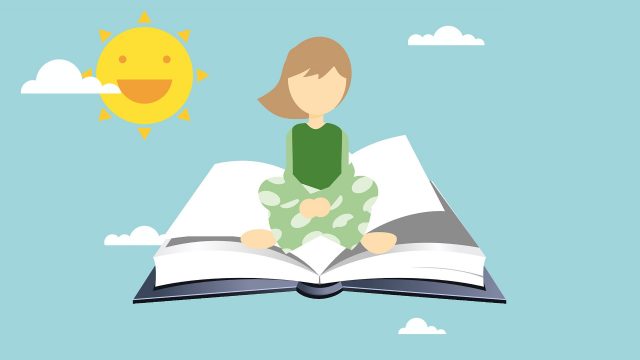こんにちはユキです。
慶弔の対応において、祝電や弔電などの電報を打つことがたくさんあります。
秘書や総務で慶弔の担当をしているあなたも、幾度となく電報の文面を考えて、電報を打っていることと思います。
電報文を考えるときに、どのような文面にしようかと悩んでいませんか?
定型文だと苦労はしませんが、気の利いた文面にしようとすると気が重くなりますよね。
実は私も秘書をしていたときに、電報の文面を考えるが大嫌いでしたが、定型文にするのはもっと嫌でしたので、悩みながら気の利いた電報文を頭をかかえながら考えていました。
でもあるときから、あんなに嫌だった電報の文面作成が苦にならなくなりました。
この記事では、大嫌いだった電報の文面作成が、どのようにして苦にならなくなったのか、私の経験談をご紹介させていただきます。
電報の文面作成を嫌々しているあなたへの参考になれば幸いです。
電報の文面作成がいやだった私が俳句のお陰で苦でなくなった
私は元来文章を作るのが嫌いで、電報の文面作成も仕事だから仕方ないと思いながら、嫌々やっていました。
そんなとき俳句を習い始めたのですが、その俳句のお陰で電報の文面作成が苦にならなくなりました。
俳句を習おうと思ったきっかけは、仕事に活かそうとかではなく、自分の堅い頭を柔らかくしたいという思いからで、近所のカルチャーセンターで俳句の講座があったので、そこで受講することにしました。
最初の受講の日に先生から受講動機を聴かれて、頭を柔軟にしたいと答えましたところ、俳句では頭は柔軟にならないと言われました。
な~んだ、そうなのか、それなら俳句を習うのをやめようかと思いつつ、暫くは続けることにしました。
そうしているうちに、会社で取引先への電報の文面作成が知らない間に苦ではなくなっていました。
それは今になって考えると、俳句が仕事に活かされたと思っています。

なぜ俳句のお陰で電報の電面作成が苦にならなくなったのか
俳句と電報文には共通点がある
では、なぜ俳句を習っていたお陰で、あんなに嫌だった電報の文面作成が苦にならなくなったのか、自分なりに考えてみました。
その大きな原因は、俳句を作ることと電報の文面を作る上で、共通点があるということに気づきました。
それは・・・・・・
俳句も電報文も無駄な言葉を省くことが大事
俳句も電報文もリズムが大事
ということです。
それぞれについて、具体的に述べさせていただきます。

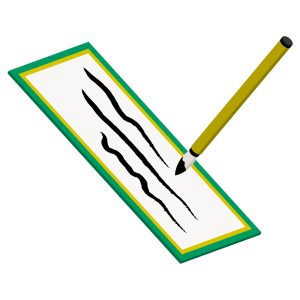
俳句も電報文も無駄な言葉を省くことが大事
ご存じのように俳句は17音の中にいろんな情報を入れて、読み手に作者の思いを伝えますので、いかに余計なことを入れないで、削ぎ落していくかということが大事です。
電報文も長くなりますと、料金が高くなったり、制限の文字数を超えてしまいますので、短い文の中で的確に思いを相手に伝えることが大切で、できるだけ同じような意味の言葉を重複して使わないようにしたり、入れなくても意味が通じるような言葉も省いたりすることが大事です。
俳句の場合、例えば「木犀の甘く香れる臭いかな」という句を作った場合、香れるというと臭いということがわかりますので、臭いは不要になります。
ですから、この場合は「木犀の甘く香れる〇〇〇〇〇」とすれば情報量が増え、例えば〇〇〇〇〇の部分に「帰り道」を入れれば、「木犀の甘く香れる帰り道」となります。
*木犀(もくせい)とは秋の季語で、金木犀や銀木犀の種類があり、9月頃に甘い香りがする花をつけます。
 金木犀(キンモクセイ)
金木犀(キンモクセイ)電報文の場合、例えば「この度の貴社ご創業50周年を寿ぎ心からお祝い申し上げます」という文を作った時に、「寿ぎ(ことほぎ)」と「お祝い」とは同じような意味ですので、「寿ぎ」を省き「この度の貴社ご創業50周年を心からお祝い申し上げます」というようにします。
また、「桜の花の咲く本日の良き日に新工場のご竣工を迎えられ、誠におめでとうございます」というような場合は、咲くのは花に決まっていますので、「花」を省いても意味が通じますので、「桜の咲く本日の良き日に新工場のご竣工を迎えられ、誠におめでとうございます」というようにします。
俳句も電報文もリズムが大事
また、俳句ではリズムも大事だとも教えられました。
良い句に沢山触れて、文章のリズム感を養うことができたように思います。
式典や葬儀の際の電報披露でいいなと思う電報文も、とてもキレのいいリズムを感じます。
ですから、私が作成した電報文も声を出して読み、リズムが踊っているか、へたっているかを確認できるようになりました。
俳句への入門で役に立った本
カルチャーセンターで俳句を習い始めたときに、通勤中の時間つぶしも兼ねて俳句の本を読もうと思いました。
そして、選んだ本が「知識ゼロからの俳句入門(金子兜太著・古谷三敏画 幻冬舎)」でした。
この本は初心者用に丁寧に書かれており、俳句とは五・七・五の音で作るというくらいのことしか知らなかった私でも、すんなりと入っていくことができました。
私がこの本で気に入った点は次のとおりです。
テーマごとに構成されていて、ページが進むにしたがってなんとなくレベルが上がっているような感じになっている
最初にそこで学ぶ内容を簡潔にわかりやすく表している
「ダメおやじ」などで有名な古谷三敏さんの漫画で、わかりやすくポイントを解説している
そのページの題材に即した有名な句を引用し、わかりやすく解説している
この本を読むだけでも電報の文面作成には充分役立つと思います。
最後に
このように俳句で習ったことを活用していくと、今までよりも質の良い電報文を作成できるようになり、嫌でたまらなかった電報の文面作成も楽しくなってきました。
電報文が苦手な方に俳句を習ってくださいと申し上げるつもりはないのですが、苦手なことを緩和するきっかけが、俳句でなくてもきっとあると思います。
私は電報の文面作成の苦手意識を緩和するために俳句を習ったのではないのですが、たまたま俳句が役に立ったということです。
そして、電報の文面作成だけではなく、手紙の時候の挨拶を考えたり、メールを打つときにも、俳句で習ったことが役立っています。
時候の挨拶については下記の参考記事をご覧ください。
あなたにも苦手なことがありますか?
もしあれば、それを克服するきっかけがきっとあると思いますので、あきらめないでくださいね。![]()